
■古民家ゲストハウスの“現地への駆け付け対応” をお願いできる方を探しています
静岡県湖西市新居町にて2025年の7月末オープン予定の一棟貸しの古民家ゲストハウス[ヨハクINN]の現地駆け付けをお願いできる方を探しています。ゲストや近隣からの苦情・問い合わせがあった場合に、現地に赴いてのアクシデント対応、必要業者の手配と報告 が主な業務内容です。交代制がとれる様に3名のローテーション体制とする予定です。
因みに湖西市内の別の一棟貸し宿の事例では、ゲスト用マニュアルの充実や張り紙での注意喚起を行う事により、アクシデント対応の頻度は半年に1回程度、 内容もトイレの詰まりを現地で解消してほしいといったものでした。軽んじるつもりはありませんが、現地駆け付けの頻度はさほど高いものではない様です。
(業務について)
業務内容 :・ゲストや近隣住人からの苦情・問い合わせがあった場合の現地対応
・状況に応じた必要業者の手配(提携先のメンテナンス業者、ゴミ収集業者へ連絡)
・宿運営者、清掃スタッフとの情報連携と報告(LINEで報告)
業務開始 :2025年7月20日予定(宿のオープンと同日)
業務期間 :毎年3/20~12/20 (初年度の2025年は 7月20~12/20)
業務時間 :1回につき1時間程度。
(担当日の 8:00~22:30は宿への駆け付けが可能な体制をとって頂く)
業務報酬 :1回の現地駆け付け毎に¥3,000。 月毎の合計額をお支払い。
宿の所在地 :静岡県湖西市新居町新居3356-1 (※新居関所跡の東隣)
駐車場 :新居関所跡の第2駐車場(無料)を利用ください
(募集人員の要件)
♢未経験の方で問題ありません。現在 2名を募集しております。
♢以下の条件を全て満たして頂く必要があります
・30分以内に現地への到着が可能な地域にお住まいの方(交通手段は問いません)
・担当日においては駆け付け要請を受けてから1時間以内に現地到着が可能な体制をとれる方(※駆け付けの対応時間は原則8:00~22:30とし、深夜や早朝の現地駆け付け対応は行いません)
※絶対条件ではありませんが、英語ができる方、男性を歓迎致します。
(現地アクシデントの想定)
・スマートキーの不具合の場合の実存キーの受け渡しと回収(実存キーは現地キーボックスに格納)
・動物、虫などの侵入
・不信者の侵入
・近隣住民からの苦情対応(騒音、その他)
・地震、火災、その他天災による被害があった場合の現地確認と委託者への報告
(ゲストハウスの概要)
・1グループ4名までの一棟貸しの古民家ゲストハウス。木造2階建、延面積100㎡程度
・営業日数(=宿泊日数)の上限は 180日/年 (※住宅宿泊事業法による)
・ICTによる無人チェックイン、解錠システム採用。(※フロントなし)
・稼働時期は毎年3/20~12/20 (初年度の2025年は 7月末~12/20)の予定
ご興味のある方は一度お話しさせて頂ければと思いますので、下記の連絡先に一報頂けますと幸いです。
連絡先窓口: いけだ建築舎 一級建築士事務所 代表 池田裕樹
E-mai: info@ikeda-archi.con
Tel : 078-380-5477
※上記のE-mailか携帯ショートメールに[ヨハク清掃 + お名前 + ご連絡先]をご記載の上、ご連絡ください。
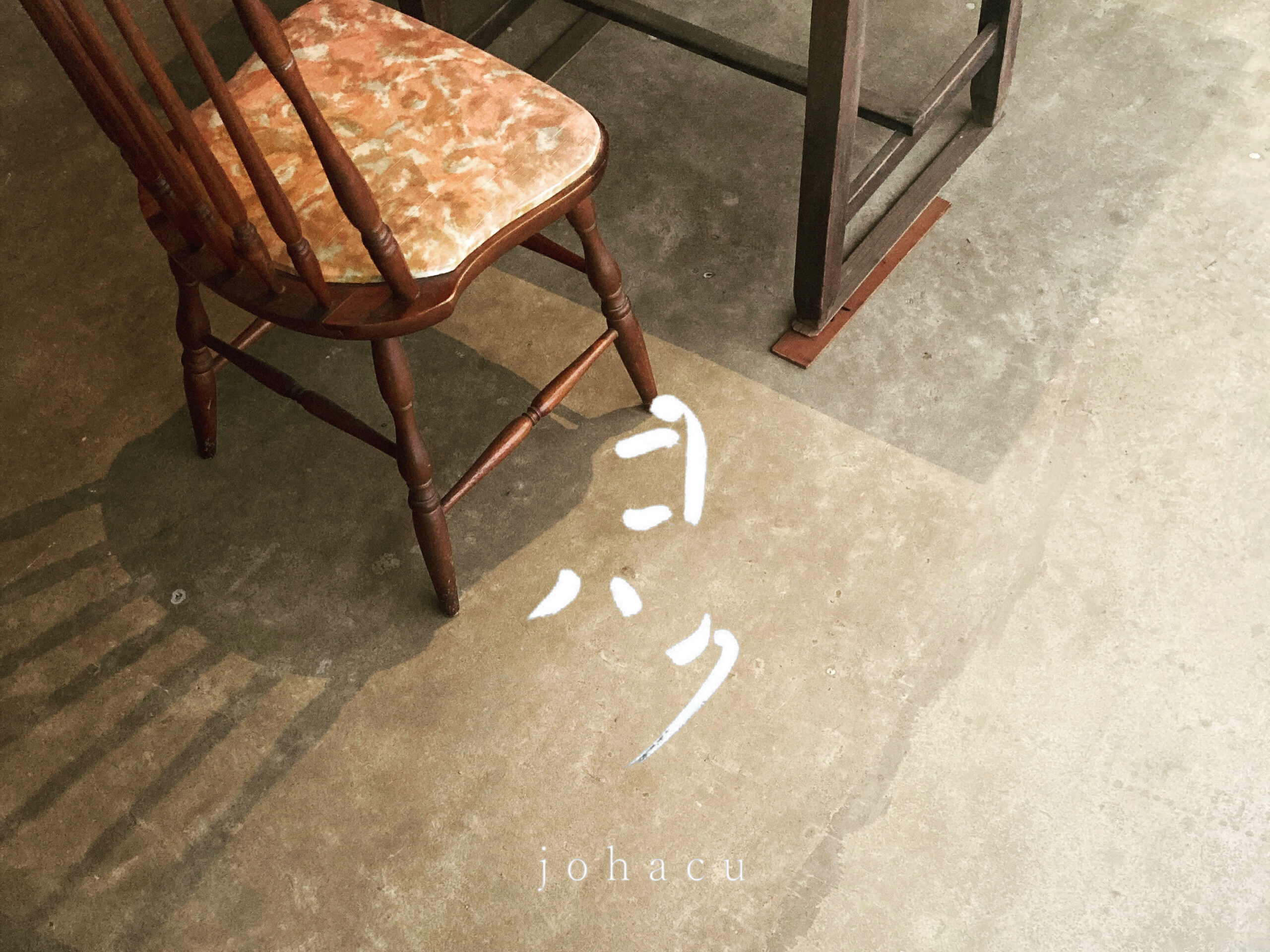




 写真の砂利敷き部分が、今回土間を打つ場所。概ね10㎡(6畳くらい)あります。
写真の砂利敷き部分が、今回土間を打つ場所。概ね10㎡(6畳くらい)あります。 三和土は 土、石灰、にがりを凡そ2:1:1の割合で混ぜて床に敷き、その上から土を
三和土は 土、石灰、にがりを凡そ2:1:1の割合で混ぜて床に敷き、その上から土を 先ずは、上記の材料を混ぜて攪拌するところからスタート。まるでコーヒー豆を焙煎してるみたい。
先ずは、上記の材料を混ぜて攪拌するところからスタート。まるでコーヒー豆を焙煎してるみたい。 そこから混ぜた土を床に巻き、順番に踏み固めていきます。いっちにー、いっちにーという感じ。
そこから混ぜた土を床に巻き、順番に踏み固めていきます。いっちにー、いっちにーという感じ。 子供と大人が一列にならんでバケツリレーで土を運びます。子供達は何往復もして次々にバケツを運んでくれてました。何と嬉しい光景でしょうか。
子供と大人が一列にならんでバケツリレーで土を運びます。子供達は何往復もして次々にバケツを運んでくれてました。何と嬉しい光景でしょうか。 ある程度まんべん無く土を敷いて踏み固めてができたら、木片とハンマーで敲き固めます。
ある程度まんべん無く土を敷いて踏み固めてができたら、木片とハンマーで敲き固めます。 裸足で踏む土は少しひんやりしてとても気持ち良いです。体がアースされていく感覚… 癖になりそう。
裸足で踏む土は少しひんやりしてとても気持ち良いです。体がアースされていく感覚… 癖になりそう。 午後はこの上に同じ要領で2層を重ね、最後は左官職人さんが鏝で仕上げました。
午後はこの上に同じ要領で2層を重ね、最後は左官職人さんが鏝で仕上げました。 今回のワークショップには地域の方々を始め、友人、仕事仲間、親族など、総勢32名もの方々にご参加頂きました。また遠くは長野県や岐阜県から駆けつけてくださった方もいらっしゃり、とても有難く自身にとってはとても幸せな夢の様な時間を過ごさせて頂きました。ご参加頂きました皆さん、本当にありがとうございました!
今回のワークショップには地域の方々を始め、友人、仕事仲間、親族など、総勢32名もの方々にご参加頂きました。また遠くは長野県や岐阜県から駆けつけてくださった方もいらっしゃり、とても有難く自身にとってはとても幸せな夢の様な時間を過ごさせて頂きました。ご参加頂きました皆さん、本当にありがとうございました!